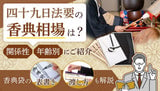おはぎとぼたもちって具体的に何が違うの?

「おはぎ」と「ぼたもち」は、どちらも炊いたもち米をあんこで包んだ和菓子ですが、食べる季節によって呼び名が変わります。
一般的に、3月の春彼岸では「ぼたもち」、9月の秋彼岸では「おはぎ」と呼ばれ、それぞれ季節の花である牡丹(ぼたん)と萩(はぎ)に由来するとされています。
また、あんこの種類や形状にも違いがあるほか、地域によっては米のつき具合によって独自の呼び名が使われることもあります。
この項目では、4つのポイントからその違いを詳しく解説します。
1. 食べる季節による違い|春・夏・秋・冬
おはぎとぼたもちは、食べる季節によって呼び方が異なるのが大きな違いです。
ただし、現在では季節を問わず「おはぎ」の名称で呼ばれることが多くなっています。
-
春のお彼岸(3月)…ぼたもち
春に咲く牡丹(ぼたん)の花が由来。「牡丹餅」とも表記する。 -
秋のお彼岸(9月)…おはぎ
秋に咲く萩(はぎ)の花が由来。「御萩」とも表記する。
夏・冬もそれぞれ異なる呼び方がある
春秋のお彼岸における名称である「おはぎ」「ぼたもち」の呼び方が有名ですが、実は、夏と冬にも異なる呼び方が存在します。
これらの名称は、言葉遊びを通じて四季を表現する日本らしい文化の一つといえます。
- 夏:「夜船(よふね)」…杵でつかずに作るため、「いつついた(搗いた)かわからない」ことを「船が夜に到着すると、いつ着いたかわからない」ことになぞらえた呼び名。
- 冬:「北窓(きたまど)」…杵でつかずに作るため、「つき(搗き)知らず」が転じて「月知らず」となり、「北向きの窓からは月が見えない」ことにちなんだ呼び名。
2. あんこの種類(材料)による違い|こしあん・つぶあん
おはぎとぼたもちは、使うあんこの種類によっても呼び方が異なり、これは小豆の収穫時期に由来するとされています。
ただし、現在では品種改良や保存技術の向上により、季節を問わずどちらのあんこも使えるようになったため、地域や家庭によっても異なる場合があります。
-
こしあんを使ったもの…ぼたもち
春は小豆の皮が固くなるため、皮を取り除いたこしあんを使用する。 -
つぶあんを使ったもの…おはぎ
秋に収穫したばかりの小豆は皮が柔らかいため、粒のまま使用する。
3. 形状による違い|丸型・俵型
おはぎとぼたもちは、形状にも違いがあるとされています。ただし、現在はこの違いが明確でない場合も増えています。
-
大きな丸型…ぼたもち
大輪を咲かせる牡丹の花に見立てて、大きな丸型で作る。 -
小さな俵型…おはぎ
萩の花に見立てて小振りな俵型にし、小さな花びら1枚1枚を模して作る。
4. 米のつき具合による呼び方の違い|半殺し・皆殺し(全殺し)
地域によっては、「おはぎ」「ぼたもち」の名称は用いず、米のつき具合(つぶし加減)の違いによって呼び方を変える場合もあります。
この「半殺し」「皆殺し」の呼び名は、主に東北地方・長野・新潟・群馬などの地域で使われる傾向にあります。
- 半殺し(はんごろし)…もち米を軽くつぶして作る(米の食感を残す)
- 皆殺し(みなごろし)・全殺し…もち米をしっかりついて作る(もちのような食感)
中には、米のつぶし具合ではなく、あんこのつぶし具合によってつぶあんを「半殺し」・こしあんを「本殺し」「皆殺し」と呼び分ける地域も見られます。
まとめ

おはぎとぼたもちは、基本的には同じ食べ物ですが、季節・あんこ・形・米のつき具合によって、呼び名に違いが見られます。
現在ではこの区別は曖昧になり、1年を通じて「おはぎ」と総称されることが増えていますが、伝統的な背景を知ることで、より深く味わうことができるでしょう。
お彼岸におはぎ・ぼたもちを食べる理由

おはぎとぼたもちは、お彼岸の定番として親しまれていますが、「どうしてお彼岸の時期に食べるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この項目では、お彼岸におはぎやぼたもちを食べる意味・理由を解説いたします。
そもそも「お彼岸」って何?
お彼岸は、春秋の年2回行われる日本独自の風習で、それぞれ「春分の日」「秋分の日」を中日(ちゅうにち)とした7日間が、「春彼岸(3月)」「秋彼岸(9月)」と定められています。
仏教では、この時期はこの世(此岸)とあの世(彼岸)の距離が最も近くなる時期とされ、ご先祖様への感謝を伝えるために、お墓参りやお供えをする風習が根付いたとされています。
また、お彼岸は、先祖供養を通じて「六波羅蜜(ろくはらみつ)」と呼ばれる仏教のお添えを実践する機会でもあります。
■お彼岸について詳しくはこちら
お彼岸とは、春(3月)と秋(9月)の年2回に行われる仏教行事です。このページでは、お彼岸の意味や具体的なお彼岸日程、4つのやるべきことなど、お彼岸の基本を解説しています。
お彼岸におはぎ・ぼたもちを食べる2つの理由
お彼岸には、おはぎやぼたもちといった小豆を使ったお菓子を食べる習慣があり、家族全員でいただくことで家族円満を願うものといわれていますが、これには具体的な理由があります。
諸説ありますが、以下に2つの説をご紹介いたします。
①小豆を用いた邪気払いのため
古くから、中国をはじめ日本などの東アジアの国では、小豆の持つ赤色は太陽や火、血などの「生命」を象徴する色とされており、邪気を払う「陽」の力を持つ神聖な食材と考えられてきました。
このように、小豆を先祖代々の霊にお供えすることで、災いを防いで邪気を払うためという説があります。そのほか邪気払いの効果によって、成仏できていない霊の魂も鎮めようとしたという考えもあります。
中国最古の薬物書には、小豆の煮汁が解毒剤として使われた旨が記されており、日本でも小豆は薬として用いられてきました。栄養豊富な小豆を摂取することで、実際に疲労回復などの効果が見られることも、魔除けの力があると考えられてきた理由の一つと言えるでしょう。
現代においても、自宅までお参りに来てくださった親族や知人へのおもてなしとして、ご親族へ疲れを取っていただくためのお茶菓子としてお出しするのもおすすめです。
②甘味をお供えして、ご先祖様に感謝を伝えるため
砂糖は奈良時代に中国から日本に伝わったと言われていますが、当時はなかなか手に入らない貴重品とされており、一部の上流階級の人々の間で薬として扱われていました。砂糖が一般庶民にも流通したのは明治時代になってからといわれています。
このように、昔は貴重品だった砂糖を使った食べ物をお供えすることで、ご先祖様への敬意や感謝の気持ちを伝えるためという説もあります。
まとめ
お彼岸におはぎやぼたもちを食べる習慣は、先祖供養の一環として広まりました。
小豆の赤は邪気を払う力があるとの考えから、小豆をお供えすることで災ぐ意味合いがあったという説や、かつて砂糖が貴重だった時代には、甘い食べ物をお供えすることがご先祖様への感謝の表れであったという説が有力です。
おはぎ・ぼたもちは、いつ供えていつ食べるべき?

お彼岸の期間は7日間ありますが、おはぎ・ぼたもちは生ものであるため、「どのタイミングでお供えすればいいの?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
結論として、おはぎ・ぼたもちは、お彼岸の中日である「春分の日」「秋分の日」にお供えし、半日から1日を目安に「お下がり」としていただくのが一般的です。
この項目では、おはぎ・ぼたもちをお供えするタイミングや、お供えした後の食べ方について詳しく解説いたします。
いつどうやってお供えすればいいの?
おはぎ・ぼたもちはお彼岸の行事食のため、お彼岸の期間内であれば、基本的にはどの日にお供えしても問題ありません。
ただし、お彼岸の中日である「春分の日」「秋分の日」にお供えするのが最もふさわしいとされています。
■お彼岸の中日にお供えする理由
お彼岸の中日は、昼と夜の長さがほぼ等しくなることから、「あの世(彼岸)とこの世(此岸)の距離が最も使くなり、思いが通じやすくなる日」と考えられています。
そのため、中日は特に力を入れて先祖供養を行うべきタイミングと考えられるようになりました。
2025年のお彼岸はいつ?中日は?
お彼岸の日程は、毎年「春分の日」「秋分の日」を中日として決められますが、国立天文台の発表に基づき、毎年若干の変動があります。
2025年(令和7年)の春彼岸・秋彼岸の日程は、それぞれ以下の通りです。
■2025年(令和7年)春のお彼岸日程
- 3月17日(月)…春彼岸入り(初日)
- 3月20日(木・祝)…中日(春分の日)
- 3月23日(日)…春彼岸明け(最終日)
■2025年(令和7年)秋のお彼岸日程
- 9月20日(土)…秋彼岸入り(初日)
- 9月23日(火・祝)…中日(秋分の日)
- 9月26日(金)…秋彼岸明け(最終日)
例年、春分の日は3月20日~3月21日ごろ、秋分の日は9月22日~9月23日ごろになるケースが一般的です。
お供えしたおはぎ・ぼたもちは「お下がり」としていただく
お供えしたおはぎ・ぼたもちは、粗末にせずに 「お下がり」として家族でいただくのが基本です。
「お供えしたものを食べてもいいの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、仏教では、お下がりとして食べることはご先祖様の供養につながるとされています。
■「お下がり」とは?
仏様にお供えしたものを下げていただく行為を「お下がり」と呼びます。
一度仏様にお渡ししたものをいただくことで、仏様への感謝や、今生きていることのありがたみを感じることができる、大切な行為であると考えられています。
お下がりは、お参りに来られた方や親族に分けたり、お土産としてお渡したりする形でも問題はありません。
お下がりを食べるタイミング
仏様へのお供え物は、一度お供えしたらしばらく置いておくのが一般的ですが、おはぎ・ぼたもちは傷みやすいため、半日~1日を目安に下げて早めにいただくようにしましょう。
もし食べきれない場合にはラップをかけて冷蔵保存し、長期保存する場合は冷凍保存も活用すると良いでしょう。
おはぎ・ぼたもちのお供え方法

お供えには、足が高くなっており仏様への敬意を表すことができる、 「高杯(たかつき)」や「盛器(もりき)」 と呼ばれる仏具を使うのが基本です。
個包装されたお菓子であれば直接置いても問題ありませんが、おはぎ・ぼたもちをお供えする際は、三角に折った半紙を敷くと安心です。
■お供えする際は、どこに置けばいいの?
- お仏壇の下段か、お仏壇の前に「供物机(くもつづくえ)」を用意した上に置きましょう。
- 高杯は左右一対(2つ)が基本ですが、盛器は1つだけで問題ありません。
- 直射日光が当たる場所や、高温多湿になる場所は避けましょう。
まとめ
おはぎ・ぼたもちは、お彼岸の中日(春分の日・秋分の日)にお供えするのが一般的ですが、お彼岸の期間中であればいつ供えても問題はありません。
お供えした後は 「お下がり」としていただくことで、ご先祖様への供養になるとされています。
傷みやすいため、半日~1日を目安に早めに食べ、必要に応じて冷蔵・冷凍保存も活用すると良いでしょう。
【レシピあり】おはぎ・ぼたもちの作り方

この項目では、おはぎ・ぼたもちの基本的な作り方を流れに沿ってご説明します。また、「おはぎを実際に作るのは難しいけど、形だけでもお供えしたい…」という方に向けて、イミテーションのおはぎもご紹介いたします。
おはぎの基本レシピ
ぼたもちは、牡丹の花のように大きめに「こしあん」で作り、おはぎは萩の花のように小振りに「粒あん」で作る形が一般的です。
基本的な作り方は同じで、もち米にうるち米(普通のお米)を混ぜたものを炊き、すりこぎで軽くつぶしたものを丸め、あんこで包んで作ります。以下に、おはぎの基本レシピをご紹介いたします。
■材料(4人前)
粒あん(こしあん)…適量 もち米…2カップ うるち米…1カップ

1.もち米とうるち米は合わせてとぎ、3カップ弱の水加減で普通に炊きます。

2.炊きたての熱いご飯を軽く混ぜ、水で濡らしたすりこぎで軽く突いてつぶします。

3.熱いうちに小さな俵形に丸めます。

4.ぬれ布巾をかたく絞ってあんを置き、ご飯をのせてあんをのばしながら包みます。

5.お皿に盛り付けたらできあがりです。
- 小豆を一から煮てあんこ玉を作るのが難しい場合には、市販のゆであずき缶を使用すると便利です。
- もち米はうるち米に比べて芯が残りやすいため、浸水時間を長めに取る必要がありますが、一晩水に浸けると水を吸いすぎてしまうため、数時間程度で問題ありません。
イミテーションのおはぎもおすすめ

「実際に作るのは難しいけど、形だけでもお供えしたい」という方向けに、おはぎをかたどったイミテーションのお供え菓子もおすすめです。
本物そっくりな質感のものや、お仏壇のお供えにもぴったりなローソクタイプのものもございます。
お彼岸の食べ物|おはぎ以外には何を食べる?

お彼岸時期の食べ物や料理は、おはぎ以外にも様々な定番品がございます。この項目では、お仏壇にお供えする定番のお供えをはじめ、お彼岸時期に食べる定番料理などを一式ご紹介します。
おはぎ以外で定番の食べ物のお供え
おはぎ以外で定番のお彼岸のお供えは、主に以下の通りです。
お彼岸団子

一部地域では、お彼岸時期に「お彼岸団子」と呼ばれるお団子をお供えする風習があります。
お彼岸の初日(彼岸入り)に供える団子を「入り団子」、最終日(彼岸明け)に供える団子を「明け団子」と呼びます。一般的には白く丸めたお団子を積み重ねてお供えしますが、地域によって形や積み方に違いが見られます。
精進料理

仏教では殺生を禁じているため、お彼岸・お盆などの特別なタイミングでは、肉や魚介類を使わずに作られた「精進料理」のお供えが定番です。
また、精進料理をお供えする際には、「御霊供膳(おりょうぐぜん・おりくぜん)」と呼ばれるお膳を使用するのが丁寧な形です。
■御霊供膳の並べ方について詳しくはこちら
御霊供膳の宗派別の並べ方や使うタイミング、メニュー例など、御霊供膳に関する基礎知識を解説します。
■フリーズドライの精進料理もおすすめ

「精進料理の準備は大変だけど、ご先祖様にはしっかりお供えしたい」という方には、フリーズドライの精進料理セットがおすすめです。
動物性の食材を使わず、昆布だしを使用するなど、伝統に基づいたお供えが可能です。お湯を注ぐだけ・電子レンジや鍋で温めるだけで簡単にご準備いただけます。※白飯は別途ご用意ください。
季節の果物

お彼岸には、お仏壇を華やかに彩る季節の果物もお供えの定番品です。長時間のお供えでも問題ないよう、リンゴやオレンジ、メロンなどの日持ちする種類の果物がおすすめです。
果物をお備えする場合も、「高杯」や「盛器」といったお供え用の器を使用してお供えします。
故人様の好きだったもの

故人様が生前好きだったお菓子(菓子折り)や飲み物をお供えするのも通例です。果物と同様に、高杯や盛器に載せて仏壇にお供えします。
仏教の教えにのっとり、お酒や肉魚などの殺生を連想させるものは避けて選ぶのが基本ですが、近年はお寿司やお酒などをかたどったローソクタイプのもの(「故人の好物ローソク」シリーズ)を代わりにお供えする方も増えています。
落雁(らくがん)

砂糖とでんぷんを含む穀粉(米や大豆など)で作られた砂糖菓子「落雁(らくがん)」も、お彼岸をはじめ、お盆にもよくお供え物として用いられます。
蓮や菊の花の形をしたものが多く、淡い色合いが特徴です。水分量の少ない干菓子のため、傷みづらく日持ちします。リアルな質感のイミテーションの落雁もおすすめです。
お赤飯・小豆めし

おはぎ・ぼたもちと同様に、小豆を使った料理であるお赤飯や小豆めしも、邪気払いの役割として定着したお彼岸の定番料理です。
還暦祝いや七五三などといった慶事でお赤飯を食べるのも、同様の理由です。
彼岸そば・彼岸うどん

お彼岸の期間には、おそばやうどんを食べる地域があり、「彼岸そば」「彼岸うどん」と呼ばれています。
「年越しそば」や「運ドン」など「そば」や「うどん」は縁起が良いとされたり、弱った胃腸を整え、内臓をきれいにする食べ物とも言われています。
天ぷら(精進揚げ)

魚や肉などを避け、野菜やキノコ類を揚げた天ぷら(精進揚げ・しょうじんあげ)も、お彼岸の定番です。
春彼岸にはタラの芽やタケノコ、秋彼岸にはきのこやナスなど季節の食材を使うといいでしょう。
いなり寿司・五目寿司

いなり寿司や五目寿司などのお寿司も、お彼岸の代表的な食べ物の1つです。
肉や魚を使わず、山菜やレンコンの酢漬けなどを使用して作ります。
煮物(煮しめ)

お彼岸期間中に毎回違う精進料理を作るのは大変なため、日持ちする野菜を使って煮物を作っておくと便利です。
定番の煮物としては、鶏肉の代わりに車麩や豆腐を使った煮物のほか、春彼岸ならタケノコ、秋彼岸なら里芋など季節の素材を使った煮物が定番です。
汁物

精進料理や和食では、「一汁三菜」や「一汁一菜」と言うように汁物を重要視します。
こちらも肉や魚を使わないけんちん汁・きのこ汁、だいこんの味噌汁などが代表的です。
■お彼岸の食べ物について詳しくはこちら
定番の「おはぎ」「ぼたもち」をはじめ、お彼岸におすすめの料理やお菓子をご紹介します。なるべく避けるべき食べ物についても触れています。
食べ物以外で定番のお供え
お仏壇には、食べ物以外にも様々なお供えを行います。仏様に対するお供えの基本は「香・花・浄水・灯燭(とうしょく)・飲食(おんじき)」の5種類とされており、総称して「五供(ごく)」と呼ばれます。
現代においては、「お線香・お花・お水・ローソク・食べ物」の5つにあたります。五供は通常のお参りにおいてもお供えするものになりますが、お彼岸は1年に2回しかない特別なタイミングになりますので、いつもより盛大に季節の花をお供えして差し上げると良いでしょう。
よくある質問

最後に、お彼岸時期の定番品であるおはぎ・ぼたもちに関してよくある質問を、ピックアップしてご紹介いたします。
Q1.おはぎは、絶対に作らないとダメ?買ったものでもいいの?
おはぎは、絶対に手作りしなければならないというきまりはありませんので、スーパー等で販売されているものを購入してお供えいただいても問題ございません。
大切なのは、ご先祖様に対する感謝の気持ちになりますので、自分のできる範囲で無理せずご用意いただくと良いでしょう。
Q2.おはぎやぼたもちは、仏壇だけでなくお墓にもお供えしてもいいの?
おはぎ・ぼたもちをはじめ、お菓子や飲み物といった仏様へのお供え物は、お仏壇と同様にお墓にもお供えいただき問題ございません。
お供え物は直接置いたりせず、半紙などを敷いて墓前の空いたところにお供えするのが丁寧な形です。お供え物の飲み物をお墓に直接かけるのは、墓石が傷む原因になりますので避けましょう。
また、カラスなどに荒らされてしまう可能性がありますので、お参りが終わったらお花以外のお供え物は基本的に持ち帰りましょう。
お彼岸関連記事はこちら
お彼岸の総合ぺージはこちらです。
お彼岸とは、春(3月)と秋(9月)の年2回に行われる仏教行事です。このページでは、お彼岸の意味や具体的なお彼岸日程、4つのやるべきことなど、お彼岸の基本を解説しています。
この記事を読んだ方は以下の記事も読んでいます。