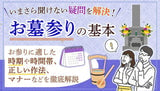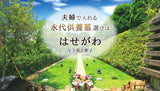樹木葬とは?種類や費用感は?

樹木葬とは、墓石を建てず、樹木や草花を墓標としてご遺骨を埋葬するお墓です。「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、許可を得た土地に埋葬されるため、一般的なお墓と同様に管理が行われます。
また、多くの樹木葬は「永代供養墓」の形式をとっており、跡継ぎ(承継者)を必要とせず、霊園や寺院が管理・供養を行ってくれるのも特徴です。
樹木葬の種類

樹木葬の形式に明確な決まりはありませんが、一般的には、施設の立地や環境によって、主に「庭園型樹木葬」「公園型樹木葬」「里山型樹木葬」の3種類に分類されます。
また、納骨方法によっても、「個別型」「集合型」「合葬型」の3種類に分類されます。
どんな場所で、どのような納骨方法を希望するかを整理し、自分に合った樹木葬の形式を選ぶことが大切です。
樹木葬の費用相場はいくら?

樹木葬の費用は、納骨形式や納骨人数、個別安置期間の長さなどによって大きく変わりますが、一般的な相場は、総額で【20万円~80万円程度】とされています。
費用は大きく分けて、契約時にかかる「初期費用」と、契約後にかかる「維持費用」の2つに分類されます。契約前には、いつどんな費用が発生するかを事前にしっかり確認しておきましょう。
※施設によって必要な費用が異なる場合もございますので、詳細は各施設にご確認ください。
■樹木葬の種類や費用について詳しくはこちら
樹木葬とは、墓石の代わりに樹木や草木を墓標とする埋葬方法です。このページでは、樹木葬の特徴や種類をはじめ、費用相場、メリット・デメリットなどの基礎知識を解説します。
どんな危険がある?樹木葬のデメリット7選

樹木葬は、管理の手間が少なく、自然に囲まれた環境で眠れる供養方法として人気を集めています。しかし、中には購入後に「思っていたものと違った」と後悔する方もいるのが実情です。
そこで、本項目では樹木葬のデメリットを具体的に7点ご紹介します。後から後悔しないためにも、事前にどんなデメリットがあるかよく確認しておきましょう。
■樹木葬のデメリット7選
1. 一度納骨するとご遺骨を取り出せない場合がある
樹木葬の納骨形式が合葬の場合は、他の方のお骨と一緒に直接埋葬されるため、後からご遺骨を取り出すことができません。
また、骨壺で個別安置するタイプであっても、一定期間経過後に合祀となる場合が多いため、将来的にお墓の引っ越し(改葬)を検討している方は、契約前に確認することが大切です。
2. 納骨人数が多い場合は、割高になることがある
樹木葬は、納骨人数ごとに追加費用がかかるケースが多いため、場合によっては一般墓よりも割高になってしまう可能性があります。
費用を抑えたい場合には、トータル予算を踏まえて検討することが大切です。
3. お参り対象が漠然としてしまう
個別の墓標を設けないタイプの樹木葬では、従来のお墓のように明確な墓標がなく、シンボルツリーなどの共通の墓標に向かって手を合わせる形が基本です。
また、基本的には共同のお参りスペースの前で手を合わせる形になるため、お墓参りの実感が湧きにくいと感じる方もいらっしゃいます。
こうした点が気になる方は、契約前にお参りの方法や供養スタイルを確認しておくとよいでしょう。
4. 交通アクセスが不便な場合がある
景観を重視するタイプの樹木葬では、自然を感じられる一方で、郊外にあるためアクセスが不便な施設もあります。
年を重ねると車の運転が難しくなるため、公共交通機関でもアクセスできるか確認しておくと良いでしょう。
5. 「粉骨」が必要な場合がある
樹木葬の中には、納骨スペースの関係上、納骨前にご遺骨をパウダー状にする「粉骨(ふんこつ)」が必須とされている施設もあります。
ご遺骨をそのままの形で残したい方や、粉骨自体に抵抗がある方は、粉骨不要の樹木葬を選ぶと良いでしょう。
もしご遺骨をそのままの形で残したい場合は、一部を「分骨(ぶんこつ)」してご自宅などで供養する「手元供養(てもとくよう)」を検討するのも一つの方法です。
供養の方法に明確な決まりはないため、ご自身の希望に合った供養方法をお選びいただくと良いでしょう。
手元供養の商品ページはこちら>>
■手元供養について詳しくはこちら
手元供養とは、ご遺骨を自宅などで保管する供養のことを指します。このページでは、手元供養の意味、メリットとデメリット、手元供養品の種類とやり方など基本を解説します。
6. 季節によって景観が変化する
樹木葬は、自然の景観を活かした墓地のため、季節によって雰囲気が大きく変わります。春から夏にかけては緑が生い茂り華やかな印象ですが、秋から冬にかけては落葉し、やや寂しい雰囲気になることもあります。
例えば、桜のシンボルツリーがある霊園では春には美しい花が咲きますが、冬になると葉が落ちて印象が大きく変わることもあります。
景観を重視して検討される方は、植えられている樹木や花の種類、開花時期などを事前に確認しておくと安心です。
7. お供え物や花のお供えはできないことが多い
樹木葬は、従来のお墓とは異なり、霊園や管理者が管理を行うため、お供え物や供花の持ち込みが禁止されている場合があります。
お線香や供花を供えて故人を偲びたい方は、契約前に施設のルールを確認し、ご自身の希望に合ったお参りができるかを確かめておくとよいでしょう。
樹木葬のメリット7選|こんな方におすすめ

樹木葬は従来のお墓とは異なる特徴を持つため、デメリットもありますが、一方で、従来のお墓に比べて費用を抑えられる、承継者不要で購入できるなどのメリットから、近年注目が高まっています。
この項目では、樹木葬を選ぶことで得られる代表的なメリットを7つご紹介します。
■樹木葬のメリット7選
1. 墓石を必要としないため、費用を抑えられる
樹木葬は基本的に墓石を必要としないため、従来のお墓と比べると、お墓にかける費用をかなり抑えることができます。
従来のお墓(一般墓)の平均費用が【80万円~250万円程度】であるのに対して、樹木葬の平均費用は【20万円~80万円程度】とされています。
一方で、複数人の納骨が必要な場合には、結果的に一般墓の方が安くなる場合もあるため注意が必要です。
※樹木葬の費用内訳は、<こちら>の項目をご参照ください。
2. お墓の承継者がいなくても安心して購入できる
一般墓は、基本的に家族が代々受け継いで管理する形式のため、承継者がいないと購入できないケースも見られます。また、将来的にお墓が不要になった場合は、承継者が墓石を撤去して更地に戻し、使用権を返還する「墓じまい」の手続きを行う必要があります。
一方で、樹木葬は永代供養が前提のため、施設の管理者に管理を任せることができ、墓石撤去も不要なことから、承継者がいない方でも安心してご購入いただけます。
3. 解放感があり、景観が豊か
樹木葬は、シンボルツリーや草花の近くに埋葬できるため、従来のお墓と比べて景観が良く、明るい雰囲気で納骨することができます。
また、自然の景観を生かした里山型などもあり、解放感を感じられる施設も多く見られます。
4. 宗旨宗派不問の場合が多い
樹木葬は、合祀・個別納骨などの種類を問わず、どの宗旨宗派でも納骨できるのが一般的です。
一方で、お寺の境内(寺院墓地)に併設する樹木葬の場合には、樹木葬であっても檀家になる必要がある施設もありますので、事前によく確認しましょう。
5. 維持管理の手間がかからない
樹木葬は永代供養が基本となっており、寺院や霊園が管理・供養を続けてくれるため、従来のお墓のように、定期的なお墓掃除や維持管理の負担がない点が大きなメリットです。
「子どもや孫に負担をかけたくない」「遠方に住んでいて頻繁にお墓参りができない」といった理由から、樹木葬を選ばれる方も増えています。
樹木葬の管理費は施設ごとにルールが異なり、個別安置中の期間のみ費用が発生し、合祀後は不要なケースや、最初から年間管理費がかからないケースなど様々です。
契約前にしっかりと確認しておきましょう。
6. ペットと一緒に埋葬できる場合が多い
仏教の「六道(ろくどう)」 という考えでは、人間と畜生(動物)は異なる世界に住むとされており、本来はペット(動物)供養は行いません。
しかし、近年は 「ペットも家族の一員」 という考えが広まり、近年ではペット専用の納骨堂や、ペットと一緒に埋葬できる区画も増えてきています。
特に、樹木葬は宗旨宗派不問の施設が多いことから、ペットと一緒に埋葬できるケースが多い傾向にあります。
7. 自然に還る埋葬形式を選択できる
樹木葬は、基本的に墓石を使用せず、自然に囲まれた環境の中で眠ることができる埋葬方法です。
特に、「亡くなった後はできるだけ自然に還りたい」と考えている方にとって、大きなメリットとなります。
ただし、樹木葬には「骨壺に納めたまま納骨する形式」と、「骨壺からご遺骨を取り出し、直接土に埋葬する形式」があり、骨壺での納骨を選択した場合は土に還ることができませんので、注意が必要です。
樹木葬に向いているのはどんな人?
「樹木葬のメリット・デメリットは色々あるけど、結局のところどんな人が樹木葬に向いているの?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。以下に具体例をご紹介いたします。
自然に還るタイプの埋葬を希望する方
墓石ではなく、樹木や草花に囲まれた環境で眠りたい方に適しています。
特に、土に還る埋葬を希望する場合は、直接土中に埋葬できる施設を選ぶとよいでしょう。
お墓の承継者がいない・管理負担を減らしたい方
樹木葬は永代供養が基本のため、お墓の継承者が不要で、家族や子孫に管理の負担をかけずに済みます。
「自分が亡くなった後に無縁墓にならないか不安」「子どもや孫にお墓の管理を負担させたくない」と考える方に適しています。
個人や夫婦だけのお墓を希望する方
家族代々のお墓ではなく、自分や配偶者だけの区画を持ちたい方にもおすすめです。
1人用・夫婦用・家族用など、施設によって区画のタイプが異なるため、契約前に納骨可能な人数を確認しておきましょう。
お墓の費用を抑えたい方
墓石を建てる一般的なお墓に比べて、樹木葬は比較的費用を抑えやすいため、あまり予算をかけずお墓を用意したい方にもおすすめです。
ただし、個別納骨タイプで長期間の安置を希望する場合や、家族全員で利用する場合には、結果的に一般墓と同程度の費用がかかることもあるため、事前にトータルの費用感で比較するようにしましょう。
■まとめ
樹木葬は、自然に還る埋葬方法を希望する方や、お墓の承継者がいない方、費用を抑えたい方にとって、適した選択肢の一つです。
しかし、納骨方法によっては遺骨を取り出せない、家族全員で利用すると費用が割高になるなどの注意点もあります。
事前にしっかりと確認し、ご自身やご家族に合った供養方法を選ぶことが大切です。
樹木葬のトラブル事例5選・対処法

樹木葬は、お墓の継承者が不要で管理の負担が少ないことから、多くの方に選ばれています。しかし、購入後に「思っていたものと違った」「事前に確認しておけばよかった」と後悔するケースも少なくありません。
この項目では、実際に起こりやすいトラブル例と、その対策を5選ご紹介します。事前に確認すべきポイントを押さえ、安心して樹木葬を選びましょう。
トラブル例① 家族から理解を得られずトラブルになった
トラブル例:樹木葬の購入後に、家族や親族からの理解を得られず、トラブルになった
対処法:事前に家族や親族との話し合いや現地見学を行い、樹木葬を選ぶことに対して理解を得る
樹木葬は比較的新しい埋葬方法のため、従来のお墓のイメージを持つ人の中には抵抗を感じる方もいます。
親が公営霊園の樹木葬に当選したものの、子どもの反対でキャンセルせざるを得なかったり、子世代が別途お墓を購入し、結果的に複数のお墓を管理することになったりするケースもあります。
購入後にトラブルにならないよう、事前に家族・親族と話し合い、理解を得ておくことが重要です。
トラブル例② 墓地としての許可を得ていない施設だった
トラブル例:購入した樹木葬が、墓地としての許可を取得していない施設だった
対処法:「墓地、埋葬等に関する法律」に基づき、墓地としての許可を得た施設かどうか確認しておく
樹木葬も従来のお墓と同じく、「墓地、埋葬等に関する法律」に基づいて審査を受け、都道府県知事から墓地としての許可を受けた土地にのみ埋葬が可能です。
しかし、中には無許可で運営されている施設も存在します。契約後に「実は墓地として認可されていなかった」と判明すると、大きなトラブルに発展することもあります。
契約前に、運営元の信頼性や、施設が墓地としての許可を得ているかどうかを必ず確認しておきましょう。
※はせがわでは、法律に基づいて正式に認可された樹木葬のみをご案内しております。どうぞ安心してご相談ください。
お近くの樹木葬を探す>>
トラブル例③ お参りの際にお供え物ができなかった
トラブル例:お供え物のルールが定まっており、お墓参りの際にお線香や仏花をお供えできなかった
対処法:契約前に供養方法や施設のルールを確認し、どのような形で供養が行われるのかを理解しておく
従来のお墓参りでは、お線香を焚いたり、お菓子や仏花を供えたりするのが一般的です。
しかし、樹木葬では火災防止や自然環境への配慮などの理由から、お線香やお供え物の持ち込みを制限している施設もあります。
後から「思っていたお参りができなかった」といったことがないよう、事前に施設のルールをしっかり確認し、希望する形式での供養ができるかどうかを確かめておきましょう。
トラブル例④ 想定よりも費用がかかってしまった
トラブル例:樹木葬なら費用を抑えられると思っていたが、実際には想定していた予算よりもかなり高くなってしまった
対処法:契約前に、費用の内訳や追加費用の有無をチェックし、トータルでの支払い額を把握しておく
樹木葬は一般的に墓石を使用しないため、従来のお墓よりも費用を抑えられると思われがちですが、埋葬方法やオプションによっては高額になることもあります。
特に、個別埋葬を選んだ場合や、プレート(墓標)の設置などがあると、費用がかさむことがあります。
契約後に管理費や法要費などの追加費用が別途発生するケースもあるため、契約前に費用の詳細を確認しておくことが大切です。
トラブル例⑤ お墓の引越し時にご遺骨を取り出せなかった
トラブル例:樹木葬へ納骨後にお墓の引越しが必要になったが、合祀型を選んだために、ご遺骨を取り出せなくなってしまった
対処法:将来的に改葬の可能性がある場合は、個別埋葬型の樹木葬を選択するか、樹木葬以外のお墓を検討する
樹木葬の埋葬方法には、合祀型と個別型があります。合祀型の場合、骨壺からお骨を出し、他の方と一緒に直接土に埋葬されるため、一度埋葬するとご遺骨を取り出すことができません。
将来的に改葬(他のお墓に移す)の可能性がある場合には、慎重に検討する必要があります。
個別型の埋葬であれば、骨壺や骨袋に入れたまま納骨が可能ですが、施設によっては取り出しができないケースもあるため、契約前に確認しておくことが大切です。
樹木葬を選ぶ5つのポイント

樹木葬を選ぶ際には、交通アクセスや納骨可能人数、供養方法など、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが大切です。
この項目では、樹木葬を選ぶ際に特に注意するべき5つのポイントをご紹介します。
ポイント① 交通アクセス
お墓参りのしやすさを考える上で、アクセスの利便性は最も重要なポイントです。
郊外の霊園では、車がないと行きづらい施設も多く、将来的にお参りが難しくならないかを考慮することが大切です。
- 公共交通機関でもアクセスできるか
- 施設内に駐車場が完備されているか
- 最寄り駅などからの送迎サービスはあるか
ポイント② 1区画の納骨可能人数
個別納骨タイプの樹木葬では、1人用・夫婦用・家族用など、区画ごとに納骨できる人数が決まっている形が一般的です。
後から区画の変更や納骨人数の追加ができない場合も多いため、将来のことも考えて選びましょう。
- 1区画あたり何人まで納骨できるか
- 追加料金で納骨人数を変更(追加)できるか
ポイント③ 合祀までの年数(個別の安置期間)
個別納骨タイプの樹木葬では、最初は個別のスペースに納骨し、一定期間経過後に合祀されるケースが一般的です。
後から「もっと長く個別で供養したかった」と後悔しないよう、個別安置の期間などを事前に確認しておきしましょう。
- 個別安置の期間がどのくらいあるか
- 追加料金で個別安置期間を延長できるか
- 年数が経っても合祀されないプランはあるか
ポイント④ 宗旨・宗派の条件
多くの樹木葬は宗旨・宗派を問わず利用できますが、寺院が管理する施設では、特定の宗旨・宗派のみ納骨可能な場合や、檀家になる必要があるケースもあります。
施設ごとに条件が異なるため、ご自身や家族の宗派に合っているかを確認しましょう。
- 無宗教でも納骨できるか
- 寺院管理の施設の場合、檀家になる必要があるか
ポイント⑤ 植えられている植物の種類・状況
樹木葬には、シンボルツリーがあるタイプ・ガーデニング型・里山型など、施設のタイプによって樹木の種類や植栽の管理方法が異なります。
施設によっては、草木の手入れが十分でない場合もあるため、現地見学を行い、実際の雰囲気や植栽の状態を確かめておくと安心です。
- 四季を通じてどのような景観になるのか
- 施設内の管理は行き届いているか
樹木葬の基本の流れ|見学から納骨・法要まで

樹木葬を検討する際、「具体的にどんな手順で進めるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
この項目では、樹木葬の見学から契約、購入後の納骨・法要実施までの一般的な流れを簡潔にご紹介します。スムーズに手続きを進めるために、事前に全体の流れを把握しておきましょう。
はせがわでは、樹木葬を含むお墓の各種ご相談を承っております。事前のご相談からご見学まで、お気軽にお問い合わせください。
1. ご見学
WEBサイトやカタログで気になる樹木葬を見つけたら、まずは現地を訪れて環境や施設を確認しましょう。アクセスの利便性や、供養・管理に関するルールも見学時にしっかりチェックすることが大切です。
2. 購入(お申し込み・ご契約)
希望に合った樹木葬が見つかったら、申し込み手続きを行います。契約前に、管理費の有無や納骨方法(個別・合祀)などの重要事項を確認しておきましょう。
公営の樹木葬の場合、抽選方式を採用していることもあるため、申込み条件を事前にチェックすることが必要です。
3. 使用許可証の発行
契約・入金が完了すると、管理者から「使用許可証」が発行されます。納骨時に必要となるため、紛失しないよう大切に保管しましょう。
4. 納骨
納骨は事前予約が必要となるため、早めに管理事務所に連絡して日程予約を行いましょう。
施設によっては、遺族が直接納骨に立ち会えず、管理者に預ける形になる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
■一般的に納骨当日に必要なもの
- ご遺骨
- 埋葬許可証…火葬後に、火葬場で発行される書類
- 使用許可証…樹木葬の契約時に、管理事務所から発行される書類
※施設によって必要なものが異なる場合もありますので、ご不安な場合は事前に管理事務所に確認しておきましょう。
5. 法要への参列(個別・合同)
従来のお墓の場合は、家族(お墓)ごとに日程を組んで「個別法要」を営む形が基本です。一方の樹木葬では、年1~2回程度、他のご家族と合同で行う「合同法要」が一般的です。
ただし、施設によっては、個別法要を希望できる場合もあるため、希望する場合は管理事務所へ事前に確認しましょう。
まとめ|樹木葬の特徴を理解し、後悔しない選択を

樹木葬は、お墓の承継者が不要で管理の手間が少ない埋葬方法として注目されています。しかし、納骨方法によってはご遺骨を取り出せない場合があるなど、注意すべき点もあります。
費用や供養方法、アクセスの利便性などを事前に確認し、ご自身やご家族の希望に合った埋葬方法を選ぶことが大切です。
樹木葬以外の【承継者不要・永代供養可能】なお墓
近年、樹木葬以外にも「承継者不要」「永代供養が可能」なお墓が増えています。ライフスタイルや供養の希望に合わせて、適した埋葬方法を選びましょう。
納骨堂(屋内墓苑)

【目安購入価格】10万円~150万円程度
屋内にあるお墓で、ロッカー式や自動搬送式などのタイプがあります。天候に左右されずにお参りができ、都市部に多いのが特徴です。
永代供養付き一般墓

【目安購入価格】170万円~150万円
従来の墓石を用いたお墓に永代供養が付いたタイプ。承継者が途絶えた際は、寺院や霊園が供養を引き継ぎます。
永代供養墓

【目安購入価格】10万円~150万円程度
最初から永代供養を前提としたお墓。個別納骨型と合祀型があり、費用や供養形式に違いがあります。
合祀墓(共同墓)

【目安購入価格】1霊につき、5万円~30万円程度
ご遺骨を他の方と一緒に埋葬する形式のお墓。費用を抑えられますが、一度埋葬すると基本的にご遺骨は取り出せません。
散骨(さんこつ)

【目安購入価格】1霊につき、5万円~70万円程度
ご遺骨を粉末化し、海や山など自然に還す埋葬方法。近年では、宇宙葬やバルーン葬など新しい形式も登場しています。
はせがわでは、樹木葬のほかにも、納骨堂や永代供養付き一般墓など、各種お墓のご案内が可能です。
もし「どのお墓を選べばよいか分からない」とお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。